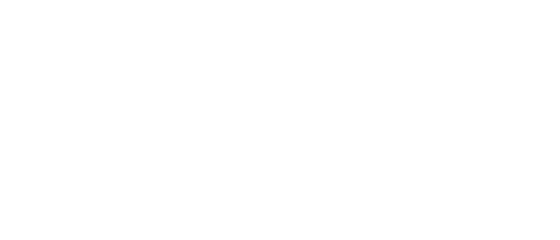俺が海で溺れていたとき、セーラとカリハは海水浴場の賑わいを眺めようとして偶然近くの岩場に来ていたらしい。
「アンタが溺れていると分かった途端、止める間もなくセーラが飛び出していったからな。仕方なくアタシもついていって、セーラがアンタを連れ帰っている間にサメと少し『お話』してやったってワケだ。ま、話せば分かるやつだったよ。ちょっとでもセーラに噛みついていたりしたら、アタシがボコボコにしてやったところだけどな!」
改めて事の顛末を聞くと、カリハは自慢するような口振りでそう語った。いかにも魚っぽい下半身のセーラと違い、カリハの腕や下半身は鱗の目立たないザラっとした質感をしている。そう、それこそ鮫のような見た目だ。ヒレの形もどことなく鮫に似ている気がする。
「ごめんねカリハ、うっかり説明するの忘れちゃってて……」
「全くだぜ、まあわざとアタシを除け者にしようとしたワケじゃないなら良いさ」
「そんなことしないよ~」
思い返してみると確かに、セーラからは「セーラが俺をこの洞窟まで運んだ」としか聞いていない。彼女も決して嘘は言っていないが、「カリハが一緒に居た」という大事な部分が語られていなかったようだ。
「そういうわけだからオマエ、しっかりアタシに感謝しろよ!」
「ああ、ありがとうカリハ。俺は2人のお陰で助かったんだな……」
「そう、分かれば良いんだ、分かればな。……で、そんなことより、だ」
カリハは急に黙り込むと、じっと俺のことを見つめ始めた。なんというか、品定めというか……俺という人間が値踏みされているような、そんな目つきだ。
「あの、なにか……?」
「オマエ……さっきまでセーラとヤってたんだよな?」
「えっ、いや、まあ、うん」
「……どっちが誘ったんだ?」
「え?」
「ふふっ、人間さんが私の体に発情してしまったので、私がそれに応えたんですよね?」
「ちょ、セーラ!?」
「なるほどなァ……だとしたら、アタシも負けてらんねぇよなぁ」
小説「うみのあな」後編
小説「うみのあな」前編
ある夏の出来事だ。
その日俺は、友人たちと海水浴をするために海を訪れていた。普段はプールで泳ぐ機会もなかなかないが、かつて小学校の授業で教え込まれただけの泳ぎ方でも、意外と体は忘れていないものだ。天気が良くて日差しが熱い、まさしく絶好の海水浴日和。夏休みシーズン真っ只中ということもあり、浅瀬は子連れの家族やカップルなんかで混雑していたが、少し岸から離れてしまえばそれだけでも、両手足を広げて水面に浮かんでいられるくらいにはスペースの余裕が確保できた。
「まさしく海に来た、って感じだなぁ……」
一緒に海まで来た友人たちは、なにやらビニールボールを膨らませて遊びの準備をしている様子だったが、こうして日頃のストレスを忘れてただ海に浮かんでいるだけの時間も悪くない。真夏の日差しを浴びながら、そんなことを考えてのんびりと海面を漂う。どうせ用があるなら呼びに来るだろうし、それまで俺はこうしていよう。──そのつもりだった。
ふと気が付くと、やけに遠くから俺の名前を呼ぶ声がした。妙に迫真の、まるで今すぐ俺になにかを伝えないといけないような、とにかく切羽詰まった声だった。
と、同時に疑問が浮かぶ。あまりにも声が遠すぎる。不意に胸騒ぎを感じた俺は、飛び起きるようにして身を起こすと、声の聞こえる方向へと目を向けた。
「な……っ」
浅瀬の方に居る友人たちの姿が、驚くほど小さく見える。いや、違う。俺が岸から離れているんだ。ただ水面に浮かんでいるつもりだった俺は、いつの間にか砂浜から大きく離れた沖の方へと流されていた。離岸流というやつだ。毎年ニュースでその名前を聞くことはあったが、まさか自分がそれを体験することになるとは思ってもいなかった。
「まずい、まだ流されてる……!?」
今なお砂浜が遠ざかっていることに気が付き、焦った俺はすぐに泳ぎ始めた。だが、離岸流は強い流れだ。本来は横にそれて流れのないところから岸に帰るべきで、流れに逆らって泳いでも体力を奪われるだけ。しかし半ばパニックに陥っていた俺は、そんなことに気づく余裕もなかった。
そして、不運には不運が重なるらしい。必死に泳ぐ俺の視界に、映画やテレビ番組なんかで見覚えのある何かが横切った。
──鮫だ。
思わず体が止まった。状況を理解するまで数秒かかる。鮫、海水浴客を襲うこともあるという海の危険生物。それが今まさに、助けも期待できないこの状況で目と鼻の先に居る。
驚きと焦りで、顔が海の中に入っていることも忘れて息をのむ。瞬間、喉の入ってはいけない場所へと海水が流れ込んできた。痛い、苦しい、怖い。
俺は、一瞬にして溺れた。
鮫が迫る。視界がぼやける。意識が遠のく。
(まずい、死ぬ)
俺の意識は、そこで途切れた。